
2026.1.31
No.2〈株式会社めい〉代表・日下部淑世、扇沢友樹「自分たちの名前が忘れ去られた後も残る“舞台”をつくる」
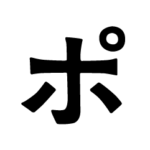
噂の広まり
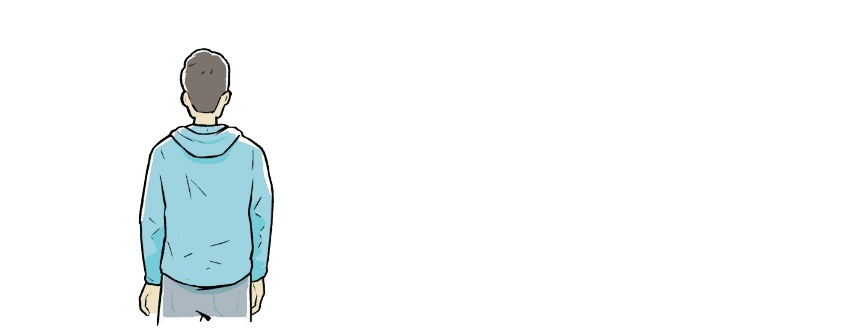
わたしたちは何のために働くのだろう。最近は、食べていくための仕事はライスワーク、金銭的利益にこだわらず人生をかけておこなう仕事はライフワークと呼び分けられることもある。けれど多くの場合、仕事は「ライス」のためであると同時に「ライフ」のためでもある。だから、わたしたちは悩むのだ。
この連載で訪ねる「文化経営者」たちは皆、京都のカルチャーを最前線で牽引し、ライスワークとライフワークを華麗に両立しているように見える。だが、彼・彼女らが歩いているのは、想像よりもずっと細く、頼りない尾根道だ。片側はビジネスとして成立しない夢物語、もう片側は、食っていくためだけのライスワーク。ひとたびバランスを崩せば、どちらかに滑り落ちていくギリギリのバランスの上に、文化経営者たちは立っている。その肩に、多くの責任や人生をのせながら。
自身も経営者である『ポmagazine』編集部の光川との対話を通じて、ひとりの人間としての彼・彼女らに近づいてみたい。

〈株式会社めい〉共同代表
日下部 淑世(くさかべ・としよ)
大学卒業後、パートナーである扇沢さんと共に「株式会社めい」を2011年に創業。以来、不動産を介して人生に寄り添う仕組みを追求してきた。職住一体型のシェアハウス運営を通じ、入居者のケアやコミュニティづくりを担当。建物という箱に「人の温かみ」を吹き込み、挑戦する人々の人生に伴走している。

〈株式会社めい〉共同代表/不動産脚本家
扇沢 友樹(おおぎさわ・ともき)
役割を終えた建物に新たな脚本を描く「不動産脚本家」。大学在学中、不動産と企業のファイナンスを学ぶなかで人口減少社会の不動産業界に関心を抱き、2011年の大学卒業と同時に株式会社めいを創業。デザイン思考とアート思考を取り入れた不動産企画を探求している。
京都・丹波口エリア。中央卸売市場が近く、かつては倉庫や工場が立ち並んでいたこの場所が今、静かに熱を帯びている。渦の中心にいるのは、「株式会社めい」の日下部淑世さんと扇沢友樹さんだ。
若手アーティストが住みながら制作できる〈KAGANHOTEL〉や、ものづくりシェア工房〈REDIY〉、空き家を改修した住宅の供給とアート作品のリースサービスを一体化した〈現代文化住宅〉など、廃墟同然の建物を次々と再生させ、人の流れを変えてきた二人。最近では元かまぼこ工場を再生した〈ふふ(FUFU)/Food Urbanite Factory Umekoji〉(以下〈FUFU〉)も始動した。





不動産を媒体に、次々と事業を生み出し続けている二人だが、その行動力とバランス感覚は、どこから来ているのか。今回は、編集部の光川が以前から親交のあるこの二人の事業哲学を聞くべく、取材を申し込んだ。
人生ゲームの「ルールチェンジャー」になりたかった

光川:お二人の活動を拝見していて、いつも思うのが「なぜ次々と新しい事業を生み出し続けられるのか」ということ。その原体験というか、最初の衝動はどこにあったんですか?
日下部:私は小学生の時に母を自死で亡くしていて。それまでは裕福な家庭だったんですが、そこから一転して「家なき子」のような状態になり、転々とする生活を送りました。その経験の中で、「人の幸せは金銭面だけじゃないよな」「豊かさはどこにあるんだろう」ということをずっと考えていて。

光川:小学生でその問いに向き合うというのは、あまりに壮絶ですね。
日下部:母の遺書に「強く生きなさい」って書いてあったんですよ。
光川:それを見て、どのような感情になったんですか。怒りなのか、それとも……。
日下部:怒りというよりは「もったいないな」と思ったんです。母は絵が好きだったり、クリエイティブな発想を持っていたりしたから。環境が変われば幸せになれたかもしれないのに、その環境をつくるスキルや精神的余裕がなかった。だから私は、自己表現をする人たちの生き方をどう応援できるか、伴走できるかということに興味をもつようになりました。
光川:たしかに日下部さんは自分自身が表現者になるのではなく、事業というかたちで、表現者に伴走されているなと感じます。
日下部:人生ゲームってあるじゃないですか。あれはお金を稼いだ人が勝ちですけど、現実の人生はそうじゃないって思うんです。「これで勝ち」みたいな指標がひとつであることへの違和感があって、私は「ルールチェンジャー」になりたいと思ったんです。自分がプレイヤーとして表現するよりも、メタな視点で、指標を変える仕組みをつくりたかった。

光川:その視点が、京都という場所を選んだことにも繋がっているんでしょうか。
日下部:そうですね。私は小学生の頃から幕末の動乱期が好きで。青春18きっぷで京都に一人旅に来た時、島原の建築「角屋」に、新撰組たちによる刀傷が残っているのを見て衝撃を受けました。普通なら直して綺麗にする傷を、あえて残している。新しいものを受け入れないようでいて、実はミーハーに受け入れつつ、残すべきものを残して伝統にしている。そのルールの混ざっている感じというか、新旧混淆(こんこう)の文化に惹かれて、中学時代から「一生京都に住むぞ」と決めていました。

お互いを心に宿す共同経営

光川:日下部さんはご自身の思想やビジョンを、扇沢さんとともに実際に事業として形にしてきたということですよね。お二人はどう、役割分担しているんですか?
日下部:基本的に、根源的な材料を持ってくるのは私です。「この場所に何かしらのヒントがあるだろう」と情報を集めて、まな板の上に乗せる。それを調理して味付けするのが扇沢ですね。お皿は私が準備して、盛り付けはみんなに手伝ってもらう、みたいな。
光川:まな板と調理人(笑)。
日下部:私はインプットしたことを抽象的に頭に残すので、言語化が苦手で。頭の中では左脳的な事象も、言葉にすると右脳的になってしまうんです。扇沢は逆で、中身は右脳的だけど、表現するときはエクセルや法律用語を使って左脳的にアウトプットしてくれる。このバランスがすごく良くて、出来上がったものが「見たことない、でも成立しているもの」になるんです。
光川:お二人のパートナーシップは本当に絶妙ですよね。理想と現実、アクセルとブレーキの役割分担が綺麗に機能している。
日下部:はい、あと彼の方が、精神衛生を保つのがうまいので。私は人間関係に興味が向かいがちで、ホテルのお客さんやスタッフ、入居者たちとのやり取りで悩むこともあるんですが、そういう時に扇沢がよく言うんですよ。「その出来事、死ぬときの走馬灯に出てくるの?」って(笑)。
光川:羨ましい関係性です。
日下部:そう言われると「確かに出てこないな」って思えて(笑)。私は心に扇沢を宿しているし、扇沢は心に私を宿している。お互いが精神的な依存先になっているからこそ、このバランスで走れているんだと思います。

「好き」が連鎖して事業が生まれる

光川:お二人の手がける事業は、シェアハウスから始まって、アトリエ、ホテル、そして今回は食品工場と多岐にわたりますが、そこには何か共通の文脈があるんでしょうか。
日下部:私、「収集癖」があるみたいで。中学時代も好きな野球選手のバッターボックスを365日撮り続けていたり(笑)。古地図や商店街の変遷を集めるのも好きなんです。そうやって集めた情報の海の中から、扇沢と共通して「好き」だと思える線を引いていくと、事業につながっていく。
光川:なるほど。具体的に、どの事業がどう繋がっているんですか?
日下部:最初は「職住一体」をテーマに、固定費を下げて生きる実験をする場としてシェアハウスを始めました。そこから、「DIYしたいけど道具を置く場所がない」という課題が出てきて、音が出せて道具をシェアできる〈REDIY〉が生まれた。
次に、「作品を作っても保管したり展示する場所がない」というアーティストの課題に応えるために、現代版の床の間をつくろうとして〈現代文化住宅〉ができた。
そして、〈REDIY〉などに入居していたお菓子作りをする人たちが、製造許可を取るための初期投資の高さに苦しんでいるのを見て、それを解決するためにつくったのが今回の〈FUFU〉なんです。

キャプション:新しくオープンする〈FUFU〉。初期投資を抑えて食品製造業の許可が取れる区画を用意し、食のチャレンジャーを支援する
日下部:〈FUFU〉は元かまぼこ工場で、食品加工の許可が取りやすい設備が残っていたんです。これを活かせば、ワンルームの家賃程度のコストで、自分の商品を製造・販売できる拠点がつくれる。これは「食」のクリエイターにとっての心強いインフラかつチャレンジの基盤になると思いました。
光川:すべての事業が、前の事業で見えた課題や、その時々の出会いから必然的に生まれているんですね。まさに「わらしべ長者」的というか。
Y字路で正しい選択をするために
光川:そうやって建物を活用して場所をつくっていくお仕事ですが、お二人を「不動産屋」と呼ぶのは、ちょっと違うなと感じるんです。ご自身たちの事業をどのように定義されているんでしょう?
日下部:完全にしっくり来るわけではないですが、あえて言うなら「大家業」が近いのかなあ。店子の暮らしそのものだけでなく、仕事や新しい関係性など、長い目で人生自体を考える。
あとは、若者のための舞台をつくるつもりで、事業をやっています。まだ何者でもない20代、30代の人たちが、ここに来ることで人生のターニングポイントを迎えて「化ける」。そんな場所を増やしたい。

光川:ターニングポイントですか。
日下部:人生を歩んでいると「Y字路」が現れるじゃないですか。どっちに進むかで人生が大きく変わる分岐点。私たちと関わったことが、そのY字路での正しい選択につながる行動であってほしい。だから、入居希望者との面談では、その人にとって本当にここが良いのかをすごく考えます。
光川:これまで、どれくらいの人数と面談されてきたんですか?
日下部:1,000人以上と話してきたと思います。「入居してほしい」と思って面談するんじゃないんです。例えば、今までお店をやっていた人が、建物の都合で立ち退きになって「一旦お店を辞めて、料理教室でも挟んでから考えようかな」と思っているとする。その時に〈FUFU〉みたいな物件は、もし本人が「挑戦したい」と思っているならベストな物件なんです。
でも、実はその発言に迷いがあったり、本音じゃない部分が混ざっていたりするならば、ここはベストではない。面談ではそれに気づいてもらうことが大事なんです。だから「実家や今住んでいるところで小さく始めた方がハッピーだよ」と断ることもある。Y字路でいかに正解を出してもらうかの方が、入居してもらうことより大事ですから。

光川: 事業を長く続けていると、日下部さんたち自身の経営においても、これまでの延長線上でいいのか迷うような「Y字路」が出現することがあると思うんです。
日下部: ありましたね。特に〈KAGANHOTEL〉を始める前、つまり借金をする前と、した後の間が、精神的に一番不安定でした。
光川: そういう大きなY字路で、どう考えてどんな選択をされてきたんでしょうか。
日下部:大学卒業後、事務所兼シェアハウスとして「めいちゃんち」の事業を始めた時点で、「最低限、自分たちの固定費を下げれば何としてでも生きていける」と分かったんです。入居者たちとお金が少ない分、ご飯を作り合ったりして。「これは一つの豊かさだね」ということが前提条件として分かった。 でも、2軒目の「REDIY」や3軒目を運営し始めた頃に、「このまま老後までこの規模感で進んでいくのか」というY字路が現れたんです。

光川: どういう迷いだったんですか?
日下部: 今は良くても、子どもが生まれたり親の介護が必要になったりと、ライフステージは変わっていきますよね。その時に今のスタイルのままで対応できるのか、と。 それまでは無借金でやっていて、先輩経営者からも「無理して規模化する必要はないよ」と言われていたし、私自身も今の幸せを噛みしめていればいいと思っていました。 でも「もしこの先、借金をしてでもやりたい事業が見つかったらどうする?」「もし見つからなかったら、このまま終わるのか」と悩んでいた時期が、やっぱりすごく不安定で。
光川: 現状維持か、リスクを取って大きな挑戦をするか。
日下部: ええ。そこで扇沢と半年くらい話し合った結果、結局「今の幸せを大事にしつつ、物足りなくなったり、やりたいことが見つかった時にはジャンプしてみよう」「その時はチャレンジしよう」という選択をしたんです。そう決めたら、もう何の言い訳もつかないじゃないですか。誰に言われたわけでもなく、自分で決めた選択ですから。そこからは精神的にも結構安定しましたね。
光川:経営者って、そのY字路の連続だと思うんです。常に「どっちに行ったらどうなる」と考え続けて、正しい判断を出し続けなきゃいけないプレッシャーがある。そこで正気を保てる秘訣は何なんでしょう。
日下部:Y字路って、一度進んでも戻れることもあるし、その先々で繋がっている可能性もある。だから大したことのないY字路は大して気にしない。重要なのは、「選択したら、もう選択した時の自分を信じる」ということですね。
例えば、スタッフが辞めてしまったとしても、その子の人生にとっても私たちの未来にとっても、勤めたこと、そのタイミングで辞めたことも含めて全てベストだった。お互いに次のフェーズがある。「あのY字路は不正解ではなかった」と思えるように進むしかないのかなと。

あと、お金のエクセルを私は見ないようにしているんです。この間、経費の立て替えで残高が数百万減っているのを見てすごく焦りましたけど(笑)。
光川:走る担当の人が通帳を見ると、足がすくんで走れなくなっちゃうから。そこを任せ合って、互いを心に宿しながら走れる共同代表というのは、最強のバランス感覚ですね。
「きれいごと」で文化経営はできない
光川:社会的、文化的な理念をもって事業をやっていると、どうしても採算性よりも理想を優先したくなりませんか? 「こうなってほしい」という理想像だけで計画をつくってしまいがちですが、それを現実目線、現場目線に戻すのは、口で言うのは簡単でも行動に落とすのはすごく難しい気がします。
日下部:そうですね。だからこそ、徹底的にリスクヘッジをした上で、「これぐらいの数字は頑張らないとね」という現実的なラインを引くんです。それが結果として、事業を継続させる現実につながっていくのだと思います。
光川:京都には、文化を背負っているがゆえに今の経済システムと噛み合わず、苦しんでいる事業者さんも多いですよね。そこで重要になるのが、さっきおっしゃっていた「見立て」なのかなと。今ある現状に対して、客観的に背景をずらして新しい物語をつくる力が、文化経営には不可欠だと感じます。
日下部:結局、きれいごとだけでは生きられないわけじゃないですか。「きれいごとじゃない」というのは、汚いことをするという意味ではなくて、「泥臭い」方です。 誰かに泥をかけるのではなく、自分たちが泥をかぶりながら、いかに楽しくやれるか。その泥臭さが苦じゃなければ、文化事業は楽しいものになると思います。
自分たちができる場所で光を灯す

光川:それにしても、これだけ次々と新しい事業を展開していくエネルギーはどこから来るんですか? お二人には「やらされている感」がまったくないのが印象的で。
日下部:ずっと精神年齢が小学生か中学生なんですよ、二人とも(笑)。与えられた宿題はやらないけど、自分たちが面白いと思ったことなら、締め切りを過ぎても、いいものをつくろうとする。私たちの事業は、言ってみれば「夏休みの自由研究」なんです。
光川:なるほど。自由研究だからこそ、没頭できる側面もあるんでしょうね。ここまでお話を聞いてきて、お二人の事業を何とくくればいいのか、やっぱり迷うんですよ。先ほど「大家業」が近いとおっしゃってましたが、その言葉では収まりきらないと思う。物理的な空間を使ってエコシステムを実現するためのプラットフォームづくり、というか。自分たちがいなくなっても物語が続く「強度のある舞台」をつくろうとされている。

日下部:私たちも土地を与えられていると思っているんです。その土地は永久に自分のものではないけれど、預かっている間は「おらが国を豊かにするぞ」みたいな。自分たちの生活を豊かにするために、京都という土地を肥やしている感覚です。 扇沢なんて、大学時代から江戸時代の大名である「上杉鷹山」が好きで、初めて会った時のTwitterのアイコンは「上杉鷹山」、メールアドレスにも「yozan」って入ってましたから(笑)。
光川:ジョン・F・ケネディが大統領就任の際、最も尊敬している日本人として挙げたことで有名ですよね。鷹山の自助・共助・扶助という「三助の思想」は、日本の防災や社会保障制度の根幹になったという話を聞いたこともあります。
日下部: 私たちのことを京都信用金庫さんや市場周りの企業さん、行政の方々が応援してくれるのも、「地域のために」という点で、同じ方向を向いているからだと思います。元々、銀行って「結(ゆい)」や「講(こう)」といった相互扶助の仕組みが集約してできたものとも言われますよね。今の資本主義社会では失われがちなそういった側面を、京都の銀行や地域はまだもっている。だから私たちはお金や助成金をもらうのではなく、それに代わる「応援」をもらって活動できているんだと思います。

光川:お二人の活動は、単なるビジネスを超えて、制度や行政のあり方そのもの、プラットフォーム側に働きかけているように見えます。
日下部:そうですね。行政をいじろうと思うと、結局はこの国をいじらないといけない。でも、それは政治家になる以外の方法でもできると思っています。 政治家になって上から変えるよりも、ここで輝く前例をつくって、いろんな人が見に来たり体験したりする中で変わっていくものがある。私たちは一点集中でもいいから、自分たちができる場所で光を灯して、直接的に世の中を変えていきたいんです。

名前が忘れられた後も残る「舞台」を
光川:先ほど、きれいごとでは生き残れないというお話がありましたが、本当はそういう本音で喋れる環境が欲しいですよね。文化に片足を置いている経営者って、仲は良くても「実は過去に失敗して」とか「こんな制度があるよ」といった生々しいところまではなかなか踏み込まないというか。だから、若い人が事業を始めた時、誰も本当のことを言ってくれないまま、谷底に落ちてしまうケースも多い。
日下部:若い子たちに「自分にもできるかも」と思わせてしまっているとしたら、時にはある種の「悪」にもなりうると思うんです。もし無防備に飛び込もうとしているなら、ライフジャケットを持って側でこっそり見守りたい、とすら思います。

日下部:なかには、不動産や経営に尽力するのがもったいないような才能を持っている人もいるじゃないですか。そういう人たちが才能を発揮するために、代わりに私たちがリスクを取りたいんです。 10年前、私たちは朱雀宝蔵町の何もない廃倉庫にテントを張って暮らし始めました。何もないところから自分たちで場所をつくる楽しさ。でも、それを続けるためには、「生きること、働くこと、暮らすこと、交流すること」について突き詰める必要がありました。
光川:その突き詰めた結果が、今の「舞台をつくる」というスタンスなんですね。
日下部:はい。プロダクトづくりって「問答」なんですよ。問答し続けないと前に進めない。そうやって問い続けてつくった場所が、私たちが死んだ後も世界の物語に織り込まれるような「強度のある舞台」になればいいなと思っています。
光川:自分たちがいなくなった後の世界、ですか。
日下部:まだ見ぬ誰かの人生のターニングポイントをいかにつくり続けるか。何も持たない20代、30代がいかに化けられるか。 私たちが死んで名前が忘れ去られても、その舞台と物語さえ残れば、世界は少しでもいいものになるんじゃないか。そう信じて、これからも問答を続けていきたいと思います。

✳︎『ポmagazine』の更新は下記からチェック!
「ポmagazine」は「Umekoji Potel KYOTO」が運営する旅のメディアです。
肩の力を抜いて、好奇心に満ちた時間を過ごしたいと願うあなたに。 京都駅から徒歩約15分、新しい京都ヘといざなう「ポテル」を旅の拠点にしませんか?
・「梅小路ポテル京都」公式サイト
・「梅小路ポテル京都」公式Instagram
企画編集(順不同、敬称略):光川貴浩、河井冬穂、早志祐美(合同会社バンクトゥ)
撮影:徳井蒼大














