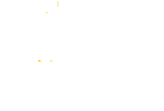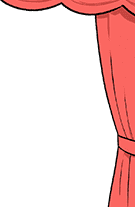2020.8.27
「いい店なのにたまにしか開いてない」、そんな場所が京都には多いらしい
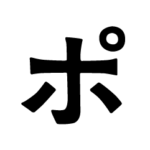
噂の広まり

人に連れて行ってもらった店で「ここ、○曜日しか開いてないんだよ」と言われると、ちょっと気分が上がる。店の紹介記事で「不定期営業のため、開いていたら来訪必須」などと書いてあると、俄然行きたい気持ちが加速する。この感覚がわかる人、結構いるんじゃないだろうか。
「なかなか開いてない」とか「いつやってるのかわからない」という言葉には、不思議な引力がある。レア感、という意味でのワクワクがひとつ。あとは、そういうところには名店が多い……気がする。(そして、いい意味での「珍店」であることも)
京都で「開いてない名店」といえば、「三吉みたらし」「らーめんや亜喜英」あたりだろうか。強烈な個性の「屋台 いなば(現在は閉店)」「スペースネコ穴」は、ある意味殿堂入り?なんて考えていたら、ちょうどこんな話を耳にした。
「ずっと気になってるんだけど、全然開いてなくて、ずっと行けていない店がある」
これはぜひともリサーチしなければ!ということで、「なかなか開いてない名店」を探してみた。その結果、想像以上のドラマが続々と……。「ポmag的・開いてない店ガイド」、お店に隠されたストーリーと共ににお届けします。
ポmagが選ぶ「開いてない名店」
今回紹介するのは全部で5店舗。その内訳は、曜日限定で営業している店が2つ、不定期営業のため事前にSNSなどでオープン日をチェックをしておきたい店が2つ、そして、なんと取材後に不定期営業から定期営業に切り替わってしまった(!)店が1つ、となっている。実際に一度で周ることはほぼ不可能。本記事限定の「開いてない店」ツアーをスタートしよう。
その1 霜月文庫
住宅が並ぶ通りに映える、白い塗り壁とタイル。鞍馬口の一角にある「霜月文庫」は、まるで絵本に出てくるような外観が特徴の古本書店だ。

「OPEN」の文字に惹かれ、2つの突き出し窓に挟まれた茶色の扉をそっと押す。柔らかく、静かな空気に満ちた5坪ほどの店内。近所に住む人だろうか、一人の男性が壁際に並ぶ本棚を静かに見つめていた。奥に座り、店内の様子を見守っているのが店主のノムラさんだ。新刊書店に勤める現役書店員でもあるそうだが、たまたまこの物件見つけたことをきっかけに、お店を持つことを決めたという。

「『あっ、この物件開いてるんだ』って思った瞬間、急にぶわーってやってみたい気持ちが膨らんでしまって。『自分だけの空間を作って、本を売ってみたいな』っていう気持ちが、もしかしたらどこかにあったのかもしれません」
部屋を借りたのは昨年の3月。約1年かけて準備に取り組み、今年の1月末に開店にこぎつけた。ご自身のペースを大切に、今のところは月に2回ほど、金曜日のみ店を開けている。

内装の改修もほとんど自分でしたという。「いい歳して、お店屋さんごっこみたいな感じですよ。大人になりきれない学生の部室みたいなもので……」と謙遜するが、天井や壁、窓の金具に至るまでご自身で仕上げてしまうなかなかのこだわりぶり。小物ひとつ、飾られているイラストひとつとっても、それにまつわる特別なエピソードが飛び出す。店内は、空間そのものがノムラさんの愛情に包まれているようだ。

本棚に並ぶのは、ノムラさんがお家から持ってきた本の数々。「長年の積み重ねですごい量になってしまって、そろそろ放出していこうと」。ノムラさんは、自身をつげ義春の『無能の人』の登場人物「路傍の石売り」に例える。
「石を勝手に路傍に並べて売る人なんですけど、それがすごい好きで。自分の好きなものを勝手に売るっていうそういうゆるいコンセプトでやってます」
とはいえ質はさすがのもので、そのほとんどが絶版本だという。河原町丸太町の名書店「誠光社」の店主・堀部篤史さんも太鼓判を押す品揃えだ。

店内を見回し、「まだまだ道半ばです」と話すノムラさん。
「小さな店ですが、もっと本を増やして、その存在感でしっかり重みを出したいですね。理想は、海外で出合った古書店。上から下まで本で埋め尽くされたようなお店ですね。テーブルや棚も足りないので、恐ろしいことに、今度またDIYをする予定です」
ノムラさんの「好き」で構成された5坪の空間は、まだまだ広がる可能性を秘めているようだ。
【霜月文庫】
金曜を中心に営業。不定期営業となることも多いため、オープン日はホームページ、もしくはインスタグラムをチェック。
・HP
その2 珈琲の店 雲仙
四条通から膏薬辻子を抜けて、綾小路通を少し西に歩いた角に立つ「珈琲の店 雲仙」。いつ訪れても常連のマダムや地元の大学生で賑わうこの店は、昭和10(1935)年創業の老舗喫茶だ。


今のご主人である高木利典さんは、この店の三代目にあたる。お祖父さんが創業し、お母さんが守ってきた店。焙煎機、カウンター、レジスター……創業の時代から働き続ける「大先輩」に囲まれ、高木さんは店に立つ。

高木さんが生まれるずっと前から、高木家の一階は「雲仙」だった。
「学校から帰ったら常連のおっちゃんの膝の上に座って、しゃべったり、勉強教えてもらったり。大きくなってからはここでレコード聴いたり、ギター練習したりね。子どもの頃はどこの家も皆こうなんやと思ってたくらい、これが当たり前やった。ここは、店というより家やねん」

営業は基本的に毎週日曜日だけ。というのも、高木さんは会社で働く勤め人でもあるためだ。
「手伝いはしとったけど、『継ぐな』って言われてたんよ。やけど5年くらい前かな、急に母親から『あんたコーヒーの焙煎ちょっと勉強しとかへんか』って言われて」
店に立つようになってから、昔はあまりにも日常だった場所の見え方が変わってきたと高木さんは話す。
京都で、こんな古い喫茶店で、椅子もレジも、みんな大事に残してもろて。本当の意味で『ああ、うちって京都の喫茶店やったんや』って気づいたような感じ。こんなんて普通は考えられへんやん。お客さんにも言われるんよ、あんたこれは無二の財産やでって」


その一方で「古いままで止まっていたいとは思わない」とも語る。メニューの内容やコーヒーの入れ方に新たな工夫を加えたり、お店のオリジナルグッズを作ったりと、挑戦を続ける高木さん。なかでも人気なのが、1年ほど前に始めたホットケーキで、それを目当てに来店する旅行客も増えているそう。「若い人が多く来てくれるようになって嬉しいね。写真撮ったりしてるのを見てこっそり喜んでます。次はこうしたらええかな、ああいうことやりたいなって考えてる時が本当に楽しいね」。
老舗であることに囚われない創意工夫と、重ねてきた歴史を大切に思う気持ち。この2つを両立させる高木さんの姿勢が、人々が街の内外から足を運ぶ居心地の良さに繋がっているのだろう。訪れた際には、刻まれる時をコーヒーと共にゆっくりと味わいたい。
【珈琲の店 雲仙】
基本は日曜営業。たまには土曜にオープンすることも。その週の開店状況はフェイスブック、またはご主人のツイッターをチェック。
その3 Gang from far far away
五条通から七条通にかけ、高瀬川に沿って広がる旧五條楽園。かつて花街として賑わい、現在もディープな空気が漂うエリアの一角に、お茶屋だった頃の面影を残す2階建の建物「五条モール」は建っている。モールに集まるのは、酒場の「えでん」をはじめ、雑貨屋や短編アニメーション専門のギャラリーなど個性豊かな面々。ここに、2019年の11月、新しい仲間が加わった。しばらく空き部屋となっていた2階のスペースに入ったのは、不定期でオープンするショップ&イベントスペース「Gang from far far away(ギャングフロムファーファーアウェイ)」。名前はイカついが、運営しているのはなんともチャーミングな3人組。全員が京都精華大学出身の同級生だ。

この場所の発案者は、もともと五条モールの運営者である「さっこさん」の知り合いだったという中西さん。さっこさんが営むモール1階の「えでん」を手伝っていたことから、2階の空きスペースを使って何かやってみないかと誘ってもらったことをきっかけに、井上さんと柳さんに声をかけた。
「井上とは、大学の入学試験で初めて話して以来ずっと友達で。専攻も一緒だし、一緒に住んでることもあって、2人のアトリエがほしいねっていう話は何度かしていました。そうしたらちょうどここが空いてるっていう話を聞いて。あと1人誘おうかってなって、専攻は違うんですけど大学で仲良しだった柳が加わってスタートしました」

「ギャング」のワードは井上さん発。
「私が『さようなら、ギャングたち』たちっていう小説が好きで、そこから『ギャング』はどう?って。それに2人がピンと来た感じ」「でも『ギャング』だけだとちょっとあれやし、後ろになんかつけよってなって」
「物騒やし、みんなギャング名乗るほど覇気ないしな」と笑う柳さん。「ちょっとアンニュイな感じ」を狙って「from far far away」を後ろにくっつけ、映画タイトルのような響きの「Gang from far far away」が誕生した。
「『なんとかギャラリー』みたいな、場所の役割が固定されるような名前にはしたくないっていう気持ちがあったんです。主にはアトリエとして運営するけど、ただ自分たちの場所としてだけ使っていくのは面白くないよねって」

現在はアトリエとして機能するほか、3人のオリジナルグッズや友達のアーティストのグッズを置くショップとしてもオープン。イベントの開催時には作家の前田流星さんや、滋賀の老舗銭湯「容輝湯」の若き女将・藤内ユキナさんなど、大学時代の繋がりを生かして、スペースを様々に変身させてきた。

もうすぐオープンから1年。テンポよく和気藹々とした会話からは、3人の仲の良さが感じられる。運営上の役割分担も「今のところうまい具合に出来てると思います」とのこと。
「理緒奈はん(井上さん)がまずアイデアを出すことが多いですね。俺はそのためにはこれが必要やな、みたいな話をして。その段階ではまだふわっとしてるのを朝美(中西さん)がキュッとまとめて『計画立てよう』ってしてくれる」「(作家で友人の)前田いわく、中西が委員長で、私が教室の後ろで『あれやろう、これやろう』って言ってるヤンキー(笑)。委員長が困った時には副委員長の柳が助けてくれる感じで、補い合ってうまく回ってます」
1人のアイデアを全員で面白がれるのが魅力の3人だが、平日にはそれぞれの職場で働き、時には個人で制作を請け負うこともある。普段の仕事にプラスして「Gang from far far away」の運営を行うことに大変さを感じることはないのだろうか。
「それはあまりないですね。むしろここが中和剤というか、遊び場所が増えたような感覚です。これからも『こういう場所だ』っていうのが固定されないように、好きなことをやれる場所でありたい」
何となく楽しいことに出合いたい気分の日は「Gang from far far away」のインスタグラムをチェック。運よくオープンしていたら、ぜひ3人のギャングたちに会いに行きたい。
【Gang from far far away】
不定期でオープン。オープン日やイベント内容はインスタグラムで告知。
その4 土と日
最近、名店が続々誕生していると噂の河原町松原界隈。とあるビルの2階に、週末だけ現れる店がある。酒と肴の店「土と日(つちとひ)」。曜日ごとに異なる店主が店を開く「喫茶テン」で、その名の通り、土曜と日曜に営業している。

「この店名は、土曜日と日曜日にやるって決まったとき、すぐにビビっときて付けました」と話すのは店主の長谷川さん。河原町通りを見下ろす大きな窓を背に、1人カウンターに立つ。

筋金入りの日本酒好きだという長谷川さん。昔から田んぼにもよく足を運んでおり、過去には京都の酒米である「祝米」の田植えに参加したことも。
「店をやってるのも、ちょっと下心があるんですよ。自分で買うだけだと、1本のお酒をずっと飲まないといけない。でも、みんなで飲んだらいろんな種類が飲めるでしょ?」
店に置かれている酒は週によってさまざま。付き合いの深い飲食店店主の毎週の仕入れに同行し、市内の複数の酒屋をハシゴ。味わいのタイプが異なる酒や、同じ酒米をつかった酒など、組み合わせにも工夫をこらす。仕入れる酒は週に2本、もちろん土日の2日で飲み切る。

日替わりのアテメニューも酒好きの心をくすぐる。この日のラインナップは、水茄子の生ハム巻きやトマトともずくの甘酢和えなど。素朴ながら間違いない、まさにシンプルイズベストといった言葉がピッタリだ。

大々的に宣伝しているわけでも、わかりやすい看板が出ているわけでもない。しかし、いい店には自然と人が集まるということか。狭い階段を上がって辿り着いたこの空間に心を掴まれ、毎週のように通うお客さんも少なくない。常連さんのなかには、他の曜日に「喫茶テン」を訪れたことについて「僕、浮気しちゃいました」と「懺悔」する人も。ここは、ある人にとっては「本命」になる店なのだ。
「土日になったら、みんなここに来てくれる。1週間のスケジュールに必ずここが入っているんだと思うとジーンとしますよね」
この日も開店してすぐに常連だという男性が訪れていた。お客さんとの話題は、近所の店の評判から恋愛相談までと幅広い。思い思いの会話とお酒を楽しむ週末。窓から見える光が、「土と日」に流れる時間の温かさを伝えている。

【土と日】
土日営業。
その5 寝台船
一乗寺駅すぐ、ギターの看板が目印の酒場「寝台船(しんだいせん)」。オープンは今年7月と、出来てまだ間もない店だ。

今年で26歳になるという店主の古川さん。「若い人がふらっと訪れやすい酒場にしたい」と始めたお店だが、駅に近いこともあってか幅広い年代の人が訪れている様子。この日は、近所に住んでいるというサラリーマンもカウンターに座っていた。

ご友人の力を借りつつ「ほぼ手作り」したという店内は、雑多な「青春の空気」に満ちている。学生時代、サークル部屋を好き勝手に改造したことがある人ならわかる、あの感じ……仲間が集まり、テンションにまかせて飾った学生会館の一室がそのまま店になったような空間に、妙な居心地の良さを感じてしまう。

2017年まで京都の大学に通っていた古川さん。店をオープンするまでには、いささかの紆余曲折があったようだ。卒業後、一度は内定した会社に就職するものの1年で退職。
「客観的にみれば、会社に勤めてた頃の毎日は順調そのもの。自分で言うのも恥ずかしいですが、それこそ『期待の若手!』みたいな扱いをしてもらったり……。僕自身も初めは『ここで頑張ってくぞ』という気持ちが強かったのですが、一方でやりたい仕事ではないこともはっきりと感じていました。仕事を辞めることへの不安と、二十代の時間をこのまま費やしていくことへの不安。比べた時に、後者の不安の方が遥かに大きいことを感じて、退職を決めました」
退職後は東日本を車で周った。貯金と派遣の仕事で食い繋ぐ、車中泊の日々。当時を「何者かにならなければという気持ちに追い立てられているようで、苦しかったですね」と古川さんは振り返る。

模索の日々を抜け、一乗寺に店を構えるに至った理由を聞いてみた。
「車中の生活に限界を感じ、ひとまず京都に帰ろうと。とりあえず後輩の家に転がり込むような感じで……。しばらくぼーっと過ごしていたんですけど、散歩中、借り手を募集しているでっかい家をたまたま見つけたんです。詳しく見てみたら、めちゃくちゃ安い。ほぼ勢いで『借りよう』と決めました」
今出川のこの一軒家が、「寝台船」のプロトタイプになった。
「学生の頃、雑然とした世界観がかえって居心地の良さを生み出しているような居酒屋がすごく好きで。せっかくでっかい家を借りたんだから、自分で作れるんちゃうかと思ったんです。よくわからん看板とかポスターを拾ってきて壁に貼ったりとかして」
すると、友達が友達を呼ぶかたちで人が集まり始め、最終的にはちょっとした店のような風格を醸し出すまでになった。とはいえ、もともと家として借りていた物件。「人が集まりすぎて、最後は追い出されました」と古川さんは笑う。
今出川を去った後は、拠点を出町柳へ。
「出町柳でも多くの夜を過ごしました。そこで出会った人達と何かできたら良いなとか、僕が若い年齢で何かを始めることで、僕より若い人たちに少しでも希望をあげられたら良いなとか、そういうことを考えるようになって。それが店を始めようと思った直接のきっかけかもしれないですね」
最終的に「寝台船」を構えたのが、ここ一乗寺。物件を見つけ、友人と一緒に店内を飾った。初めこそ知り合いの来店が多かったが、最近では京都の大学生や近所の住民がふらりと訪れたり、遠方からの旅行客が来店したりといったことも増えてきているという。

まるでちょっとした青春映画のような話だ。これまでがその映画の第一章だとすれば、第二章は、この「寝台船」から始まることになる。「とりあえず死なないように頑張りたいですね」と笑う古川さんだが、船出は順調の模様。というのも、記事制作中に寝台船は「開いてる方が珍しい店」ではなくなってしまったのである。お客さんが増えたことを受け、現在は日曜定休で営業しているとのこと。旅先で、学生時代に戻ったような夜を過ごしてみるのも悪くない……そう思ったらぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。
【寝台船】
現在は日曜定休で営業中。
「開いてない店」の根底にあるもの
取材中「たまにしか開いてない店って、京都っぽいよね」と誰かが言った。
今回訪れた5店舗は、店のカラーや店主の置かれている状況はまちまち。しかし根っこには、なにか通じているものがあるように感じる。必要以上に儲けようというのではなく、手が届く範囲で、自分が自分である時間と場所を作ること。
小さくとも何かを始めようとする……そんな人の背中を押してくれるのが、京都という街の空気なのかもしれない。
企画編集:光川貴浩、河井 冬穂(合同会社バンクトゥ)
写真:原祥子
企画協力:髙橋 藍、平岡さつき